ああ、この部屋は冬でとっぷりと満たされている。
鍋の湯気で、窓ガラスが白く曇っていた。
扉をあけたときから、鼻の奥をくすぐっていた匂いのもとは、ガスコンロの火に煽られて、鍋のなかでぐつぐつと滾っている。
今朝は部屋の掃除と溜まったメールの返信に追われていたから、まだなにも食べていない。
ぐう、とわたしの気持ちを代弁するかのように鳴いた腹の虫の声は、愉快そうな笑い声にうまくかきけされた。
フリーランスを志して参加したこの講座も、はやくも明日で最終週を迎えようとしている。もうすっかり家族みたいに馴染んだわたしたちは、休日の今日も朝からパソコンとにらめっこし、お腹が空いたと口々に言い合って食卓を一緒になって囲む。毎日顔を合わせているのだから、休日くらい外出したっていいのに、仕事に向き合う真摯さと、みんなで談笑する時間の柔らかさを毎日大事に味わっていた。
「信じられないなあ、この心地よい空間は、来週のいまごろにはなくなってしまっているんだな」というさびしい事実にいつも頭のどこかを小突かれながら、そんなこと気づきもしないかのように、みんな目の前の鍋に夢中になっていた。
滑らかな味噌のスープのなかで、食べごろですよと言っているように見える具材たちを丁寧に自分のお椀によそう。白菜、かまぼこ、えのき、水餃子、春雨、鶏肉、葱、銀杏、油揚げ、お餅…それぞれがすきなものを持ち寄って満たされた鍋は、いまのわたしたちそのもののようだった。なんて美味しそうなんだろう。
「いただきまーすっ」
熱いスープが唇から舌、喉、食道とするすると降りて、お腹の真ん中がじわじわと熱を帯びる。窓の外に目を向ける。今日はよく晴れた土曜日で、ここから一見するとあたたかな陽気だが、11月も終わりを迎えようとしている金谷は、既に冷え冷えとしている。
しかし、わたしはいまあたたかさに包まれている。お腹の真ん中から、靴下のさき、お椀を包み込む指の先にある爪、みんなの「美味しい」という吐息をひろう耳まで、ぽっかぽかだ。
この部屋は冬でとっぷりと満たされている。それと、あたたかな幸福で。
油揚げを噛んだら、じゅわ、と味噌が染み出した。熱は、ちりちりと舌先を焦がすけれど、箸は止められない。鶏肉を頬張りながら白い息を吐き、白菜を口に運び、冷えた日本酒をすこしだけはさむ。誰かがいじられているのを笑いながら、BGMで流れているウルフルズを口ずさんでいると、わたしのそれに乗せるような誰かのちいさな歌声を耳の裏でとらえた。
自分のための、自分らしい生き方を模索しているわたしたちは、ここで既に自由は幻想なんかじゃないと自分で気づいていた。
ここを出て、みんなどこへ行ってしまうのだろう。外は風が強くて、肩をぎゅっと縮こまらせずにはいられない寒さなのに、けれど、ひとりで、どこかへと行ってしまうのだろう。
まだ暦の上では11月で、これから冬の本領が発揮されることを知っていても、願わずにはいられない。みんながここを出る頃に、冬の寒さが和らいで、この先を明るく照らすような春の芽吹きが、それぞれの足元にありますように。わたしたちとじゃない、他のだれかとこうやって食卓を囲むことになったとき、やっぱりそこには、あたたかな幸福が満ちていますように。
鍋の具をお代わりして、追加の分をスープのなかに流し込み、それが煮えるのを待ちながら白米をかき込んでいたら、「食べすぎだ」と笑われた。「だって、美味しくて幸せなんだもん」と、更に頬張る。気持ちのままの言葉を言えるって最高だ。それを言っても、受け止めてくれると知っていることは、もっと最高だ。
鍋の湯気で、窓ガラスが白く曇っていた。そのせいで、外はよく見えない。本当に春がそこに立っていたとしても、ちっともおかしくないな、と思った。



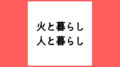
コメント